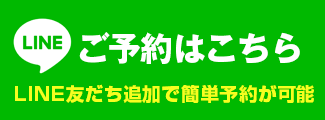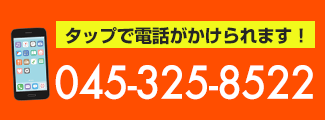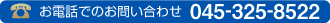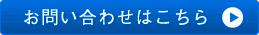寒さでパフォーマンスが落ちる理由――鍵は“自律神経”と“脳の働き”にあった

気温が下がる季節になると、「動きが重い」「集中力が続かない」「ケガをしやすい」といったパフォーマンス低下を訴える方が増えます。これは単なる“冷え”の問題ではなく、自律神経と脳の働きに深く関係しています。
特に気温が10℃以下になると、筋肉や関節の温度が低下し、神経伝達の速度が落ちることが分かっています。さらに、寒さは身体を守るために交感神経を優位にし、血流が中心部に集まる現象を引き起こすため、筋肉の柔軟性や反応速度に影響します。
こうした生理的変化は、アスリートだけでなく日常生活の動作にも影響し、肩こり・腰痛・疲労感の悪化につながることもあります。
今回のブログでは、「寒さ×自律神経×脳」の視点から、なぜ冬にパフォーマンスが落ちやすいのかをお伝えしていきます。
寒さが脳の反応速度を落とし、動きが鈍く感じる理由
脳は筋肉を動かす“司令塔”であり、どれだけ素早く信号を出せるかがパフォーマンスを左右します。
しかし、体温が下がると神経の伝達速度が低下し、筋肉が本来の速さで反応できなくなります。具体的には、筋肉温が1℃下がると筋力発揮が約10%低下するとも言われており、動きのキレが悪くなるのは身体の怠慢ではなく“脳と身体の連携低下”が原因です。
また、寒さによる末梢血流の低下は、脳への酸素供給にも影響し、判断スピードや集中力にも負担をかけます。そのため「冬はミスが増える」「考えがまとまりにくい」と感じる方も少なくありません。
自律神経が乱れると筋肉も硬くなる――冷えと緊張の悪循環
気温が低くなると、身体は熱を逃がさないために交感神経を高めます。
これは防御反応としては正しいものの、交感神経が過剰に働くと筋肉は常に軽い緊張状態になり、肩こりや腰痛が起こりやすくなります。
さらに、交感神経が優位になると血管は収縮し、筋肉への血流量が低下します。これにより、乳酸などの疲労物質が流れにくくなり、「常に体が重だるい」「力が入りにくい」という状態が続きやすくなるのです。
このように、寒さは単に筋温を下げるだけでなく「自律神経のバランスを崩す→筋肉の質が低下→パフォーマンス低下」という連鎖反応を引き起こします。
カイロプラクティックが冬のパフォーマンス低下に有効な理由
カイロプラクティックは、脊椎の歪みを整えることで自律神経の働きを安定させ、脳と身体の情報伝達をスムーズにします。特に冬は自律神経の切り替えがうまくいかず、交感神経が過剰に働きやすいため、背骨の機能を最適化することが大きな効果を生みます。
背骨が整うと、
・脳への情報入力が正しくなる
・筋肉の反応速度が元に戻る
・血流が改善し深部の温度が維持される
・疲労が抜けやすく、動きが軽くなる
といった変化が起こり、冬でも本来のパフォーマンスを保ちやすくなります。
アスリートだけでなく、日常生活で「冬は動きが悪い」「寒いと調子が崩れる」と感じる方にも非常に有効なアプローチです。