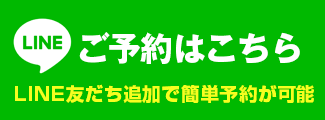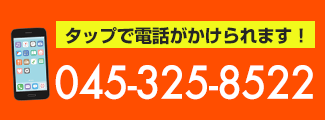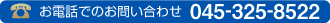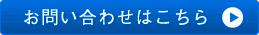発育と自律神経の関係性とは?

子どもの成長には個人差がありますが、身長の伸びがゆるやかだったり、思春期の始まりが遅かったりすると「発育の遅れ」として不安を感じることがあります。
遺伝や栄養の影響はもちろん大きいのですが、近年注目されているのが「自律神経の安定」と発育の関係です。自律神経は、ただ体調を整えるだけでなく、成長ホルモンや性ホルモンの分泌リズムに大きな影響を与えるため、子どもの発育と深く結びついているのです。
今回のブログでは、発育と自律神経の関係性についてお伝えしていきます。
自律神経が発育に与える影響
自律神経は交感神経と副交感神経がリズムをとりながら働き、体の活動と休息を切り替えています。
日中、交感神経が適度に働くことで血流が良くなり、筋肉や骨に必要な栄養が届けられます。そして夜になると副交感神経が優位となり、心身をリラックスさせて深い眠りへ導きます。この眠りの時間にこそ成長ホルモンが多く分泌され、骨や筋肉が伸び、体が修復されます。
つまり、交感神経と副交感神経のリズムがうまく切り替わることは、発育を支えるための基盤なのです。
リズムの乱れがもたらす発育への影響
しかし、夜更かしや過度なストレス、不規則な生活が続くと、この自律神経の切り替えが乱れます。
本来、夜にしっかり働くはずの副交感神経が十分に働けなくなると、睡眠が浅くなり、成長ホルモンの分泌が妨げられます。その結果、骨や筋肉の発達が遅れることにつながり、発育全体に影響を及ぼす可能性があります。
発育を支えるためにできること
子どもの発育を助けるためには、栄養や運動と並んで、自律神経が安定して働ける生活リズムを整えることが欠かせません。
日中は体をよく動かし、夜はゆったり過ごして深い眠りにつける環境をつくることが大切です。また、体の歪みや緊張を整えるケアは、自律神経のバランスを改善し、血流やホルモン分泌をスムーズにするサポートになります。
発育の遅れは単に「体が小さい」「思春期が遅い」といった表面的な問題ではなく、その背景に自律神経の働きが関わっていることがあります。
自律神経が安定していると、成長ホルモンや性ホルモンがリズムよく分泌され、体は自然に成長の力を発揮できます。
📞 ご予約・お問い合わせはこちらから
TEL:045-325-8522
LINE:QRコードを読み取り、トーク画面からお気軽にメッセージをお送りください。

🏥 Nakajima整骨院
〒231-0063
神奈川県横浜市中区花咲町2-65-6
コウノビルMM21 7階
🕒【診療時間】
月〜金:10:00~20:00
土曜日:10:00~14:00
※日曜・祝日はお休みです。